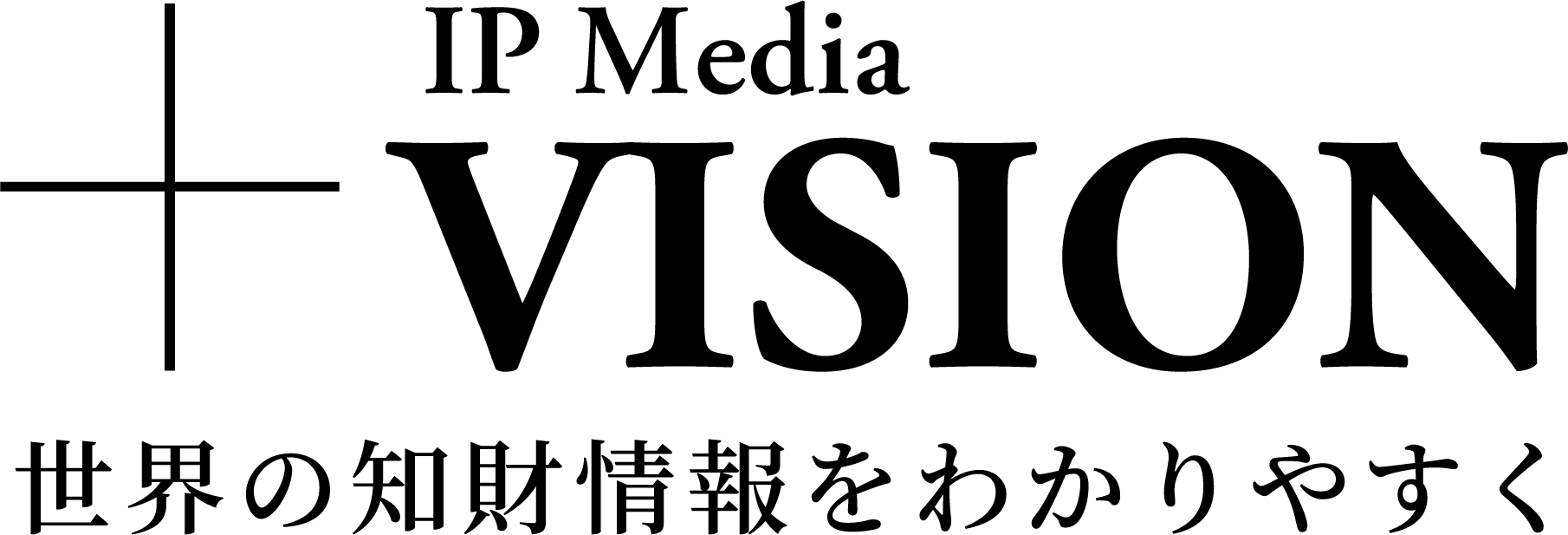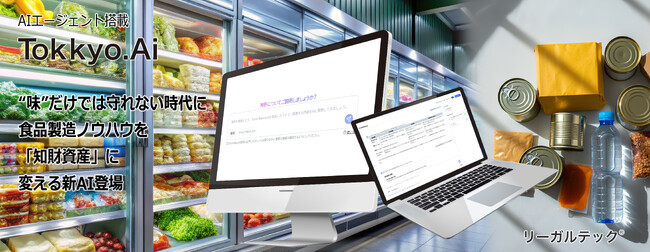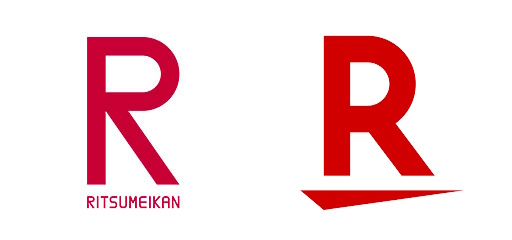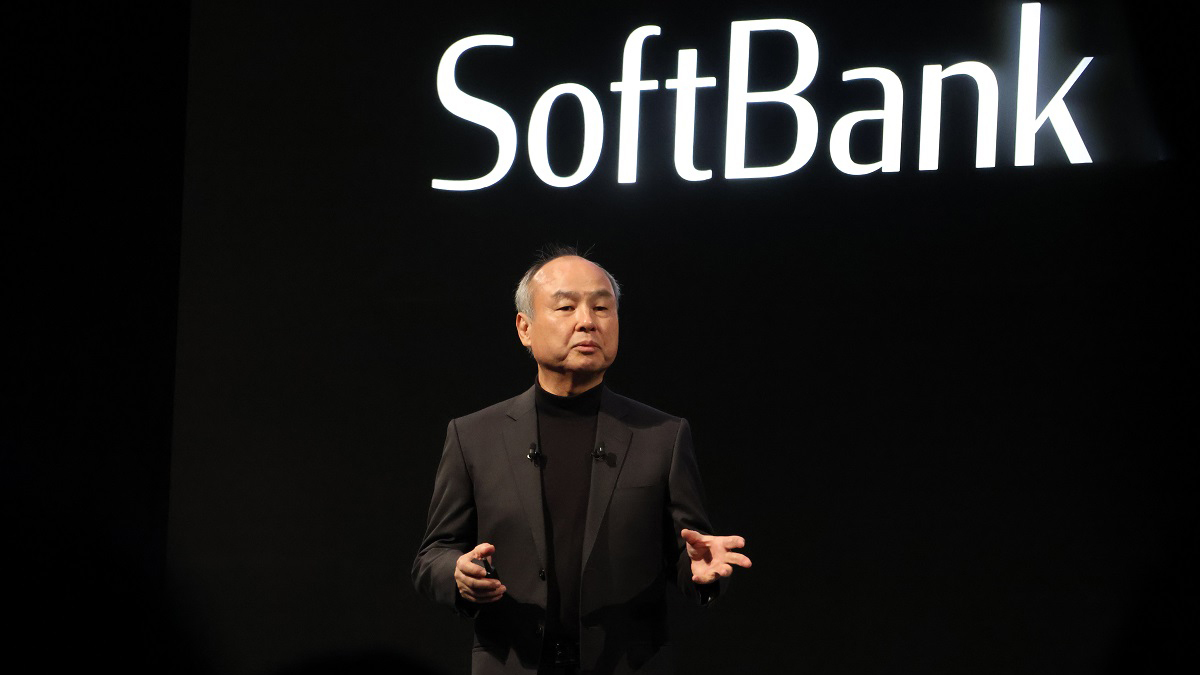建設DXサービス「SPIDERPLUS」を提供するスパイダープラス株式会社(以下スパイダープラス)にて社外CIPO(知的財産最高責任者)を務める谷口将仁さん(株式会社MyCIPO・代表取締役)をはじめとした、知財・広報・IR担当者様に話をうかがいました。
従来日本型の研究開発の成果としての特許出願ではない、顧客満足・顧客価値を守るための想いのこもった知財戦略に、新たな特許の在り方の未来が見えてきます。具体的な基礎特許のご紹介とあわせてお送りします。

谷口 将仁
MASAHITO TANIGUCHI
上場企業からスタートアップまで、複数社のCIPO(最高知財戦略責任者)を歴任。
経産省から知財功労賞の受賞、内閣府から知財経営の成功企業として事例化。
株式会社MyCIPOを設立し、国内唯一のレンタルCIPO®事業を展開。
2022年よりスパイダープラスに参画。知財戦略を統括。
CONTENTS INDEX

工事現場監督のあくなき戦い
スパイダープラスが続々と取得している一連の特許・サービスを紹介する前に、おそらく多くの読者にとって異業種であろう「建築業」の現場が、どのように仕事を進めているかについて共有するところから本項を始めたい。
というのも、各種の特許・サービスがいかに価値あるものかをお伝えするためには、まさにそのサービスを必要としている人たち、今回であれば建築に携わる方達が抱えている課題を認知してもらうことが土台になるからだ。
工事現場には「現場監督」がおり、その業務は多岐に渡るが、最も時間の掛るのが毎日の検査・レポーティングである。法律にのっとり、現場での施工が適切に行われているかを、自分の目と大量の写真で確認をし、それを帳票化する。現場が大きくなるほど当然写真は増え、1日に数百枚を処理することも珍しくない。その一つ一つが仕様通りに行われていることを確認する膨大な作業だ。
建設現場においてはまだまだICT化が進んでおらず、このレポート作成においては、以下のような地道な方法が取られているケースも多い。
・デジカメ、スマートフォンなどで撮影された写真をPCフォルダに移す
・1枚1枚ファイル名をリネームする
・写真を帳票であるExcel上に手作業で配置していく
誤解を恐れずに言えば、「まだそんなことを?」というようなPC作業を、しかし誠実に懸命に夜なべして行っている現場監督が、2020年台になった今なお存在しているというのだ。
また、現場で施工に問題のある箇所を見つけたとする。その場合どうするかというと、現場の各所を誰が担っているのかという情報が記載された「施工体制図」をデータ、あるいは貼りだされている紙面で確認し、時には事務所に置いてある資料を取りに往復してから、該当の担当者を探して声をかける…といった、これまた地道な仕事か行われる。
25年前の創業当時、スパイダープラスがまだ工事の請負会社であった頃、しばらくこうした現場の文化にのっとり、アナログ図面に線を引きペンだこを作っていた創業社長・伊藤氏は、2010年を超えiPadが登場した頃、「世の中はこんなにIT化を謡っているのに私たちはなぜ色鉛筆を握って紙に埋もれているのだ」と、建設業の課題を解決するべく自社を建設業のDX化を推進する今の会社へと進化させた。これが、工事現場監督の業務に画期的なメスを入れることになる。

特許技術が救う、建築業のDX化
こういった背景の上に、スパイダープラスはタブレットで完結する現場監督業務の仕組みを作り上げた。
「大量の現場写真は、すべて図面上に表示される各所のカメラアイコンに直接収納できるようになりました。サービス上でカメラアイコンを押せば、そのままタブレットで撮影ができる。撮影データはそのまましかるべき場所に格納され、アイコン上に撮影完了枚数が通知の数字のように表示される仕組みです。ただデータ保存ができるだけでは、アイコンをタップして、写真を確認して、という手間が挟まりますが、枚数表示機能もつけることで、確認作業時間は90%近く短縮されました。」と、同社にて知財戦略を統括する谷口氏は説明する。
谷口氏は自身の会社も経営しつつ、社外から知財責任者の役割を引き受けている日本初の「レンタルCIPO®」である(※「レンタルCIPO」は、株式会社MyCIPOの登録商標です)。
先に紹介した基本特許技術「写真枚数表示」の機能により、直感的に撮影した写真枚数が分かるため、検査進捗を簡単に把握することが可能になり、また写真の撮影漏れやクラウドで共有された情報の確認漏れなど現場作業の手戻りを防止でき、(コーポレートサイトより)作業負担は激減した。
続く特許は「写真指示削除」で、これは同サービス内で写真撮影の指示(どの向きからどのような部位を何枚撮影するのか、など)を矢印なども用い可視化するとともに、撮影完了時にその指示を削除できるようにすることで進捗管理をしやすく、見落としを格段に減らす技術である。もちろん、こうして準備された写真データをもとに、ボタン一つで帳票を吐き出すことも可能である。
そして、多数の事業所の方がかかわる複雑な施工体制図もすべてサービス内で閲覧、指示、連係できるようにと「施工体制管理」の特許技術が組み込まれている。これまで物理的な移動や、事業所ごとのUIの違いに文字通り奔走していた現場監督者の仕事は、タブレット上でワンストップで完結できるようになった。共有もクラウドで行われ、伝達不足によるヒューマンエラーのリスクも減る。
「デジタル化されていない現場」を知っていただければ、これらの特許技術がどれほど働く人にとって心強く、大願であったかについては語るまでもない。

基本から海外展開まで「攻める」知財戦略
これらの画期的な技術・特許があるのは、スパイダープラス内に確固たる知財への方針があるからだと谷口氏は語る。
「社内では、売り上げから逆算して特許を取る形にしています。日本企業は昔から研究開発の成果を出願していくというスタンスで特許を扱うケースが多く、事業化に繋がっていかない。一方でAmazonやGoogleは売上、つまりお客さんが価値を感じてくれた部分、その顧客価値を知財で特許として押さえるという方針で、うちも同じです。自社の顧客価値をきちんと定義して、その価値を日本一・世界一にするためのアイデアを発明に昇華して、特許を取って守っているというのが知財戦略の全体方針です。戦略的に取り組んでいますよ。」
「施工体制管理」の特許についてプレスを出した直後、投資家たちが一気に立ち上がったのも、時の運ではなくこだわりぬいた戦略ゆえ。プレスの時点でIRと協力し、業界の根深い課題を解決している特許の本質が伝わるように、文面に強く留意して表現しているのだそうだ。
「実際、これまでどれだけ大変だったかがわかると、特許の価値の高さが伝わります。建設業界の人には確実に刺さるし、そうでない人にも価値が伝わるように背景を丁寧に書きました。」実際コーポレートサイトやプレスを見れば、専門外の人間でもするすると情報が入ってくるのがわかるはずだ。
「知財情報を開示は、コーポレートガバナンス・コードの改訂を受けて行っています。日本の会社はまだまだ開示する企業は少ないですから、うちは知財ガバナンスを先行してやっている企業ですね。」
同社は2020年に上場しているが、IPOに向けて企業価値を上げていくために知財戦略に本腰を入れた。それ以前からサービスを始動していた同社は、タブレットがWebの延長としかまだ認知されていない2010年台から業界内において先駆的な存在であったため、後追いされる立場であったことも知財を重視した大きな理由だと谷口氏は語る。当時外部顧問的立場だったところから、IPO後さらなる戦略を展開すべく、正式に執行役員として加わった。
 スパイダープラス株式会社が各国で取得した様々な商標や特許の登録証
スパイダープラス株式会社が各国で取得した様々な商標や特許の登録証
そしてサービスの進化、特許取得を重ねながら、今後は東南アジアへの進出も検討中だそうだ。すでにPCT国際出願の調査レポートで「特許性あり」が出ているので、検討が進み次第、その国に移行しマーケットを展開していく予定だ。
「東南アジアは日系の建設会社のメインどころの海外進出先です。国土が日本の様に狭くて、そこに建物を作るとなると高層に作ることになる。だからこそ安全性のある日本の会社が受注していっている、そこに我々のニーズがあると考えています。現地のグループ会社にも導入してもらったりね。」と、どこまでもロジカルに谷口氏の、そしてスパイダープラスの知財戦略は続く。

ゆえに、「守る」知財。
最後に、日本ではまだ新しい積極的で緻密なこれらの知財への考え方は、決して温度のない冷徹なものではない、ということをお伝えしたい。
当初は社内で自分たちの仕事を楽にするために生まれた技術だったそうだ。それを、共に働く現場の人たちとともに悩み、声を取り入れながら研ぎ澄ませていった、そういった「これまで」の縁や重なり合った技術の層を守るのにも、特許取得は大きな意味があったという。
「お客さんたちと一緒に作ってきた機能を守っていこうというのが最近の社内の流れです。自分たちが現場にいたからこそ見えた課題や実状、そこにお客様の監修が加わったからこそ、現場で堪えうる専門性の高さと品質が保持されています。価値を一緒に作るというか、顧客価値を守るというのはそういったものを守ることにも寄与していると言えますね」と、同社で長く歴史を見守ってきた広報・佐々木氏も、当時を振り返りつつ語ってくれた。
「実は社長自身はIT分野にうとい(自称)ので、『自分でもわかるように』とはよく言われます。」場を和ませてくれた、その「視点」もまた、ともすれば心理的にハードルの高いICT導入を現場が受け入れ変革していくための誠実な気配りなのだろうと感じた。
特許を使って利益を上げる、あるいは技術を占有し業界内での舵取りをするといった形で注目されることも多い知財戦略だが、そこに守るものがあるがゆえに強く、真の意味での「戦略」が生まれるという、心地よい熱量があふれていた。