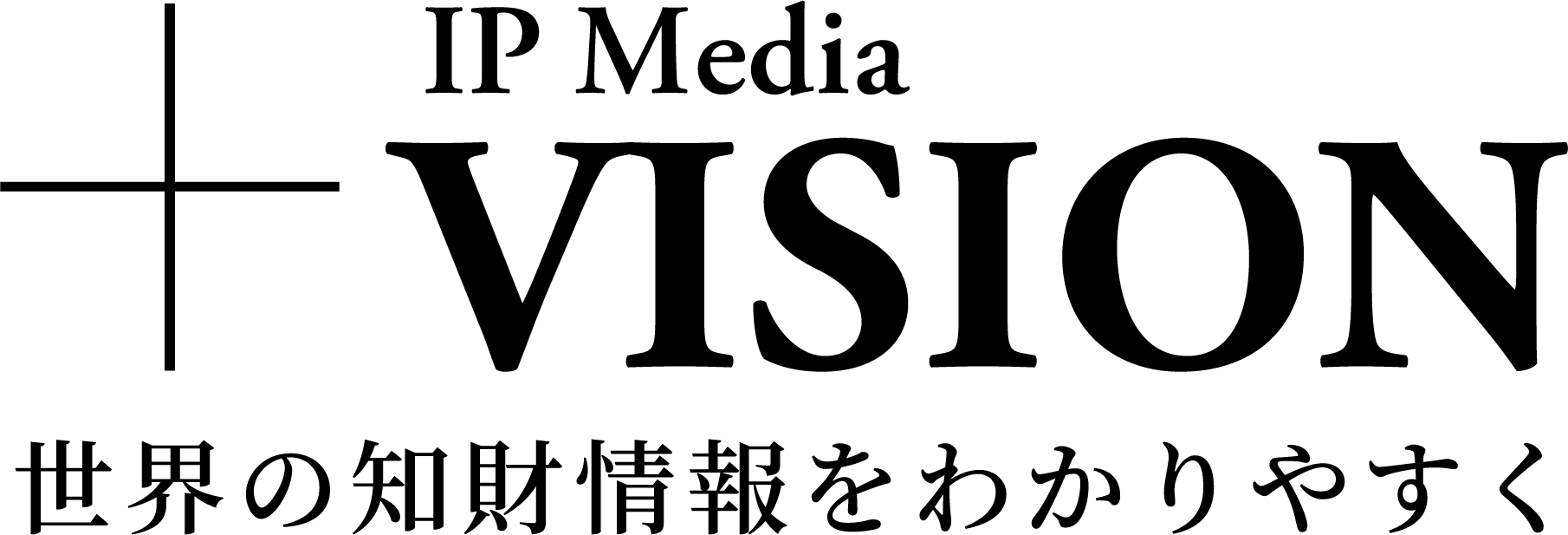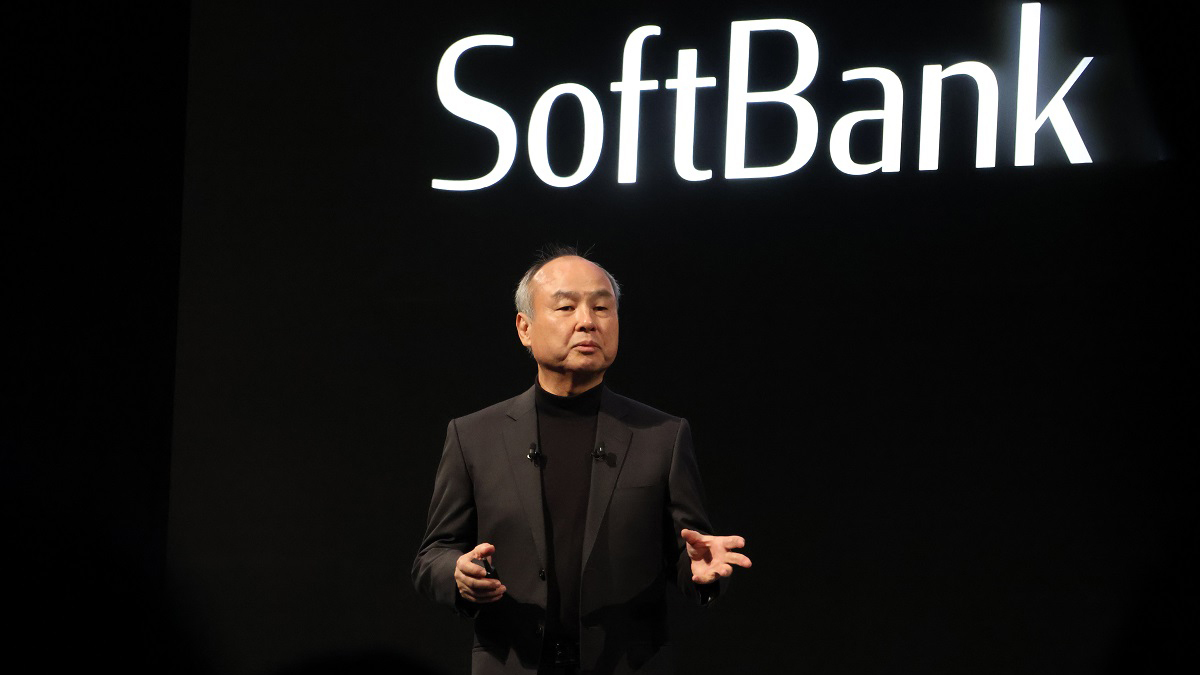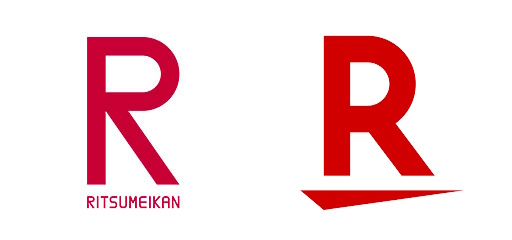ラジコンの進化版…というにはすでに市民権を得ている「ドローン」。
そんなドローンをただのロボット・おもちゃとしてではなく、「人に役立つAIを作る」と立ち上がった本郷飛行機株式会社。
研究畑から飛び出した社長・金田氏は「AIや画像処理」「小型化」「日本製」というキーワードで新しい領域を俯瞰する。その原動力になった「憧れ」と、それを実現した「技術」について、開発者兼経営者としての目線を捉える。

金田 賢哉
KENYA KANEDA
本郷飛行機株式会社 代表取締役
2010年に東京大学工学部航空宇宙工学科
2012年に東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程を卒業。飛行機やロケットの、エンジンなどを研究。
在籍中クラウドファンディングの「READYFOR」で開発兼マーケティングを行う。
さらに、家電の遠隔操作IoTサービス「Pluto」で代表取締役を経て
2016年に本郷飛行機株式会社を設立、代表取締役就任。
ドローンに関する豊かな知識識と経験でコンサルティング及び開発を行う。
CONTENTS INDEX

空飛ぶAI、新しいドローンの視点
今回はドローンの研究開発を行っている本郷飛行機株式会社の創業社長である金田氏に、令和になり新しく展開していくドローン産業の現状とこれからを熱く語っていただいた。研究者として「空を飛ぶ」という関心から生まれた本郷飛行機株式会社のドローン。そこに乗せられた夢について探る。
すでにロボットとして市民権を得て、若者を中心に一般でも取り扱いができるようになっているドローンそれ自体についてはこの紙面で説明するまでもないだろう。空飛ぶラジコン、というようなイメージのドローンだが、実際現在ドローンを取り扱っている会社の多くはラジコンを取り扱っていた企業だという。
一方、「うちは、AIの会社なんです」と金田社長。従来の空を飛ぶラジコン、というホビーの要素だけではなく、「機体自体は関連会社で製造して、運用していく中での画像をはじめとする様々なデータを収集してAIをかけるといったサービスを行っている」のだそう。画像処理やデータ分析を中心としているのが特徴だという。
これはそもそもの企業の成り立ちに端を発する。
企業理念である「人と機械の共生を目指せる頭脳を創る」というコンセプト通り、もともと本郷飛行機株式会社は大学の研究から始まったのだ。
「たまたま『真ん中にある』のがドローンであって、頭脳となるAIを作るのが目的なんです」と語る。ヒトとAIを繋ぐ、その間を本郷飛行機株式会社のドローンは自由かつロジカルに飛び回る。ドローン以外にも、地上を走るロボットも取り扱っているが、現代社会においては、空間認識をするAIの技術の発展が求められているそうだ。
「宇宙ステーションの中にもドローン的なものが飛んでいます。人間が入り込めない場所であったり、常駐しづらいところ、そういうところに、産業用のロボットの目が求められています。」
「ところが、車なら大きなセンサーがつめるけど、それはバイクにはつけられませんよね。軽量化する必要のあるドローンや、工場内を走る小さいロボットにも困難だし、産業用ロボットにつけるにしても、既存のものは量産するのは難しいんです。」
車が車間距離を自動で計測して走行を止める仕組みなどはすでに流通して久しく、品質も年々上がっている。これが「空間認識」の技術なのだが、車においては高品質であっても、金田氏が語るように、簡単に別の現場、別の機械に転用することは難しいという背景がある。
しかし、その中でも、現在の画像処理やAIの技術を拡張させ、マーケットを横に広くしていきたいと、ブレイクスルーを探る思いは強い。

創業の思い
そもそもなぜこの業界に飛び込んだのでしょうか?と尋ねると、「特に理由はないんです」と意外な回答。しかし、研究から出発したという金田氏の開発について伺うと、大学の航空学科航空宇宙工学専攻を卒業しておられるとのこと。
学生であった当時、航空関連に就職する人は少なかった。同期がカーメーカーやコンサルタント職などに就く中で「飛ぶことをやり続けられたらいいな」と思い、研究開発を続けることにしたそうだ。
「いつぐらいから飛行機が好きかと言われると、記憶がないくらいから。それこそラジコンを飛ばしていたりとか、空港に遊びに行ったりとか」と語る金田氏同様、もしかすると読者の中にも空に憧れていた子供時代がある方もいるだろうか。
ドローンについては、学生時代に設計をしてひとつのものを完成させたいという思いがあり、当時の後輩と一緒に大学の後押しもあり取り組んだのだそう。当初はそこで「大学の研究」として着陸させるつもりだったが、ビジネスにしてみては?と後輩と話した結果、当時すでに学生ベンチャーで会社運営を経験していた金田氏の牽引で起業することに。
その当時の1社目はIoTの分野で少し畑は異なるが、ビジネスをする、ということ自体に抵抗がなかった金田氏の度胸と嗅覚、そして大学での学びを直結させ市場に切り込んだ辣腕で、初年度から売り上げが立ち、以来黒字経営が続いた。

市場を制す、セルフメイドの武器
そんな躍進目覚ましい金田氏の強みを伺ったところ、「商品としては2つ」と、金田氏は語る。
「自動であることがまず1つです。開発当時に出回っていたドローンのほとんどはGPSを利用して飛ぶラジコンなので、操作は手動ベースです。自動化しているものもありますが、元々の機体を改造して自動化する流れが多い。」
「一方弊社ではハードウェアを全部作っています。多種多様なパーツや素材を買ってきて、組み立てる。そうやって、設計からやっているのが結構珍しいんですよ。そして、やはり細部に個々が日本製であることのクオリティの差が出てきます。これは明確な強みの1つです。」
「それから、屋内での飛行も可能であることがもう1つの強みです。屋内が飛べるっていうことがどういうことかというと、小回りが利いて障害物…これはモノもヒトもですがそれを避けられるという点ですね。ドローンのカメラが写したものをリアルタイムで画像処理し、検出して避ける。繰り返しになりますが、これが買ってきたハードだと大きくて飛べるサイズじゃないんですよ。でもここではゼロから作っているから。小さく軽く、それでいてGPSよりもよりよい精度でオペレーションできます。」
そもそも屋外で飛ばしているイメージのあるドローンだが、屋内にも活躍の場が?と尋ねたところ、屋内屋外問わずに活躍のニーズはあるようだ。
「そもそもまだやっている人がいないから、屋内での活用は取りあげられないだけですね。操作自体に許可がいったりもするし、外で飛ばしているのが目立つから、結果的に屋外のイメージがあるのでしょう。実際、ホビーとしてではなく産業ロボットとしても、プラントとかで人がただただ往復して巡回していたところを自動化できると大きいですよね。」ニーズはいたるところにあると考えています、と市場を見渡す金田氏、我々にはまだ見えない世界を、彼の作り出す技術が飛び交っているのだろう。
ちなみに、何度か出てきた「画像処理」についても、その速度は一級品だという。リアルタイムで与えられた画像情報を瞬時に処理し、人が通りかけたら止まったりというだけではなく、すさまじいスピード感で行きかう「スポーツの世界」のマルチアングル化にも貢献の期待が高まる。インタビュアーも前のめりにスポーツとのコラボについて意見を交わしたところ、ふむ、と展望を語ってくれた。
「確かに、視点が変わると気づくことがあります。そう、そうです。ボールを認識して追いかけることも可能です。今でもメジャーリーグとかだと球筋を動画に重ねて可視化したりしますよね。画像処理が早くなるほど、そういった精度も上がります。」
デジタルカメラで撮っても、その後プレビューできるまでにタイムラグがあるのは、経験があるだろう。その「ラグ」が画像処理の時間なのだという。そのズレがあるから、これまではドローンで撮影した画像というのは補助的にしか使えなかった。
それが本郷飛行機株式会社のドローンであれば100分の1秒での処理が可能だ。「ほぼ、今」と形容されたその通り、今その瞬間を画像から判断し、モーションに反映できる圧倒的技術、詳細は割愛するが、かなりの期間と資金お費やして開発され、現在は特許も取得しているそうだ。

開発者の目に映る特許とドローンの「これから」
金田氏がはじめて特許を取得したのは、前職時代、10年ほど前とのこと。 今の会社では6年前と、創業7年目の会社の最初期から特許については意識をしているようだ。当時まだ在学していた金田氏と協働者となった後輩は大学の知財部から勧められ関心を持ったのがきっかけだそうだ。
「国の制度を使う場合なんかは、成果のひとつとして特許を取ることも求められます。それから、戦略的に必要なものは随時取っていっていますね。」と語る金田氏、最初は画像処理のハードウェアの構成についての特許を取得し、自動着陸の制御やアプリケーションの運用とその領域を拡大させた。
「海外にもオフィスがあるので、肌感覚ですが、日本より特許に厳しいという感じはありますね。取っていかねば、という。ドローン業界は特に厳しい点があって、国内ではできないこともあるんです。法律上ね。それで、じゃあ海外でやろう!となるわけです。でもそういったときに、提案に対して、『じゃあそれはパートナー企業と実現します』とかなると海外では重ねてややこしい。だから、そういったときのためにも特許は取っておかないと、という部分があります。」
そういった知財戦略もすべて現在は金田氏が自ら実施しているという。開発者であり、研究者である金田氏らしいスタイルだ。
「今まで研究寄りの案件が多かったんです。だからここからは、貯めてきた技術を活用して、自社商品として出していける状況にしていきたい。もちろん、すぐに商品化するわけではないですが、そこを軸足にできるといいですね」と、今後の展望について語る。
大空の下でも精密さを求められる屋内でも、ドローンが人間と変わらない、あるいは人間を超える視界で、生活や産業のパートナーとなる日もそう遠くないのかもしれない。