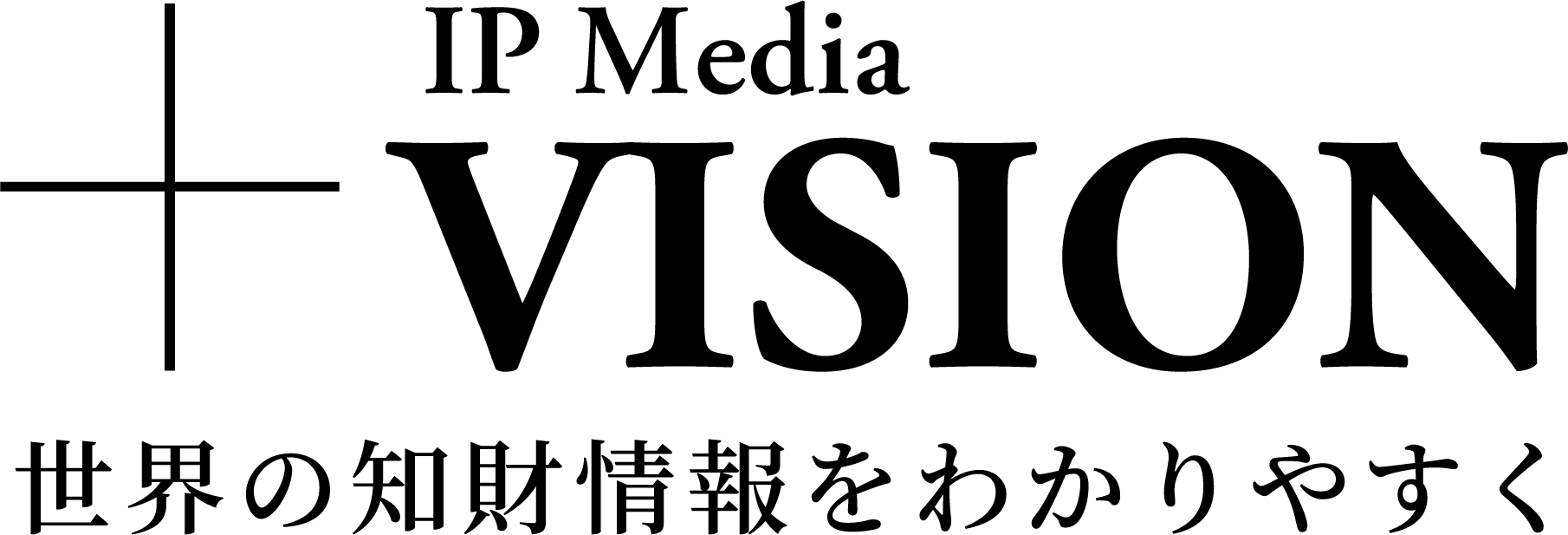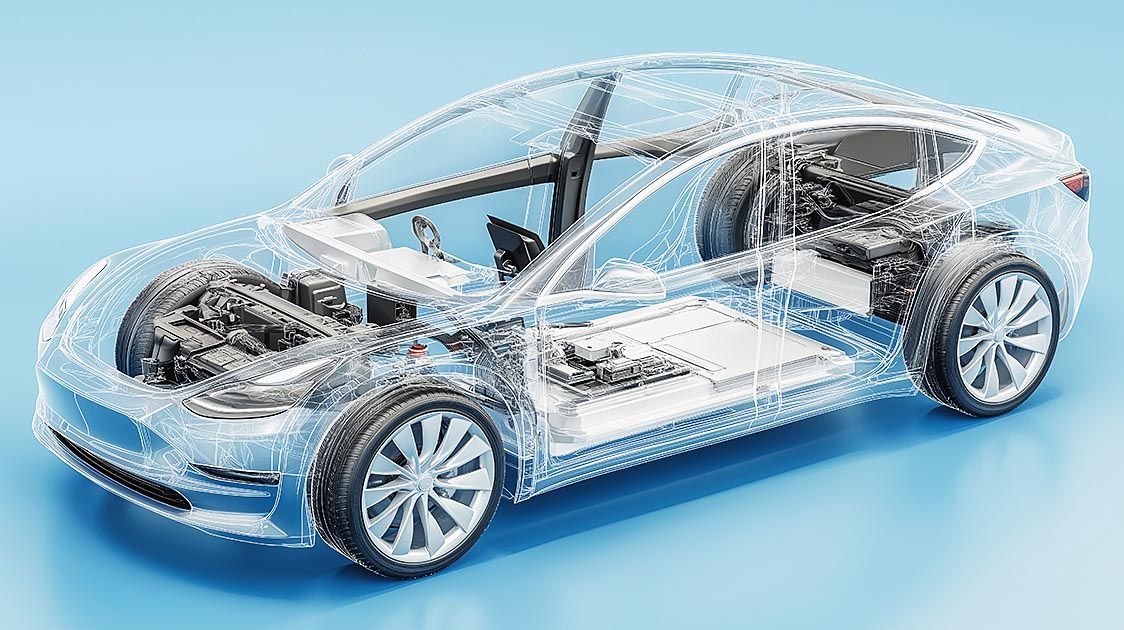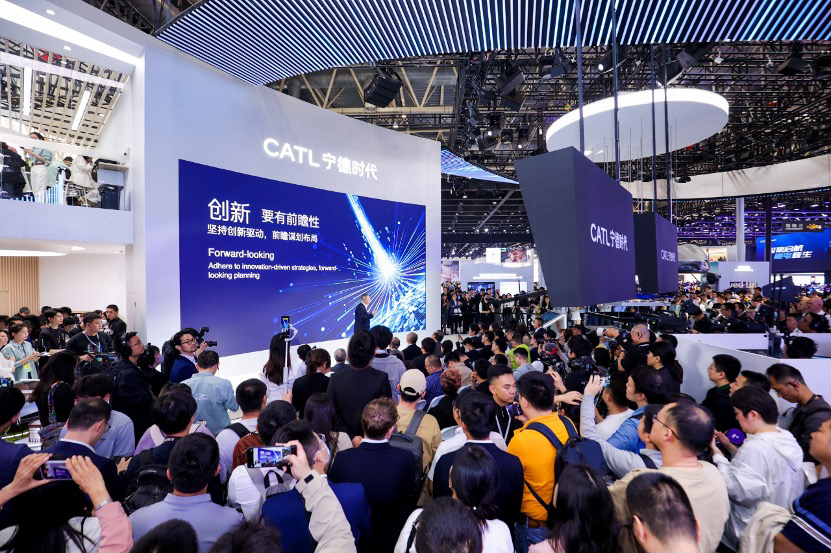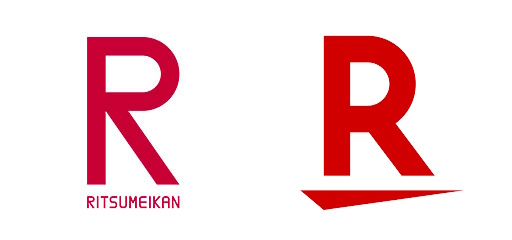ものづくりスペシャリストの為の情報ポータルメディア「MONOist」は2021年2月10日、特許は技術者のノルマではなく権利だと報じている。
特許の取得は、明細書を準備し、特許庁に出願することから始まる。出願の1年半後に出願内容が特許公報として公開される。特許の権利化を目指すのであれば、出願から3年以内に特許庁に審査請求を行う。大変なのはむしろここからで、審査結果が戻ってくるが、初回はほとんど拒絶となるため、新規性と進歩性が認められるよう審査官とやりとりを進めていく必要がある。
CAE (computer-aided engineering)や実験および知財のコンサルティングを行うアステロイドリサーチ代表取締役社長の安武健司氏は、シャープに在籍中にCAEや設計、実験、生産などに広く携わってきた。その中で多くの特許を取得し、退職後も特許収入を得てきたという。 安武氏は「特許取得は“ノルマ”と捉えられがちだが、そうではなく技術者の“権利”だと思う。なぜなら研究開発をしているからこそ、特許の出願が可能になるからだ」と強調する。
とはいえ、安武氏もはじめは特許をノルマとして捉えていた。積極的に取り組むようになったのは、自身の特許が初めて他社で使われて実施報奨金を得たときだという。さほど高額ではなかったが、その特許が使用され続ける限り、20年の期限が切れるまで、定期的に特許収入が得られる。幸いなことに、シャープでは退職しても特許収入は得られるようになっていた。この体験をきっかけに、特許収入がどんなものか、特許がどのように企業の戦略に影響を与えるかなど、実感できたそうだ。
安武氏は「論文は実施した内容だけを書けばいいので、はるかに単純。それに比べれば特許明細書はかなり煩雑で手間がかかるが、それでも技術者は特許取得に取り組むべきだ」という。
特許出願の際、請求項(メインクレーム、サブクレーム)や実施例を記載するが、実施例としてアイデアベースでもよいので想定される使用場面の列挙や素材を限定しないなど、なるべく特許のカバーできる範囲を広く取れるように書くことが重要になる。メインクレームよりも、この実施例がむしろ他社製品に引っ掛かることが多い。この点は、実験およびCAEから得られたデータなど、事実のみを書く論文とは大きく異なる。「技術者は自分が実際にやったことしか書かない傾向がある。そのため、『他にもこんな使い方ができるのではないか?』と常に考える練習が必要だ」(安武氏)という。
公的機関や社内の知財部門が、技術者としての能力を客観的に証明してくれるということも、特許を取得するモチベーションになる。特許を持ち、さらに収入もあれば、社内でも発言力を高められる。「管理職でも特許を持っていないことが多い。特許の取得や収入自体が、その技術の価値を証明してくれる」(安武氏)。
また「CAEの専任者だと、製品開発に直接はつながらないため、自分が役に立っているのか分からなくなることがある。自分の特許が実際の製品に使われているということは、大きな自信になる。むしろ技術開発の仕事に長年携わっているにもかかわらず、特許を持たないままであれば、ただのオペレーターと変わらないともいえる」と安武氏は述べる。
せっかく自分で開発した製品なのだから、きちんと知的財産権で守る。特許は、技術者が取り組んだ証しであり、その技術が製品に欠かせないものであり発表されていなければ出願しない手はない。むしろ、他社に出願されると自社がダメージを受けることになる。特許の取得は、技術者と会社の双方にとって意義のあるものであり、積極的に取り組んでいくべきだろうと「MONO ist」は報じている。