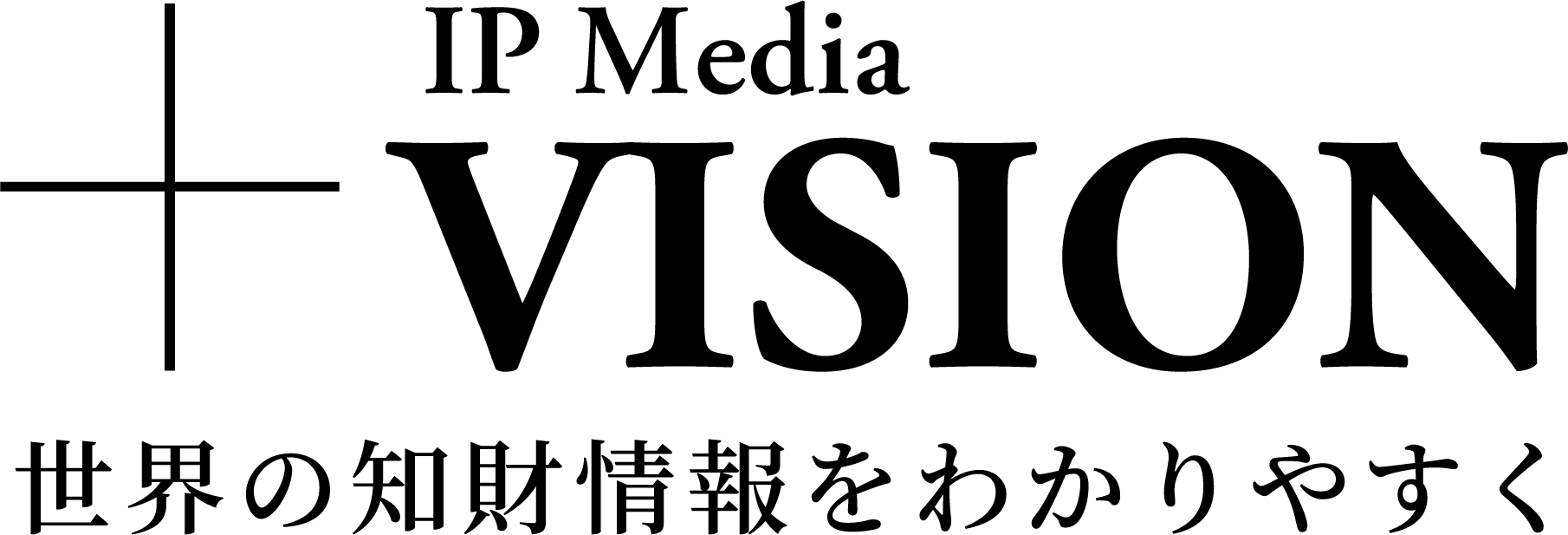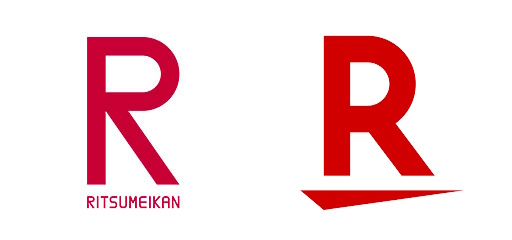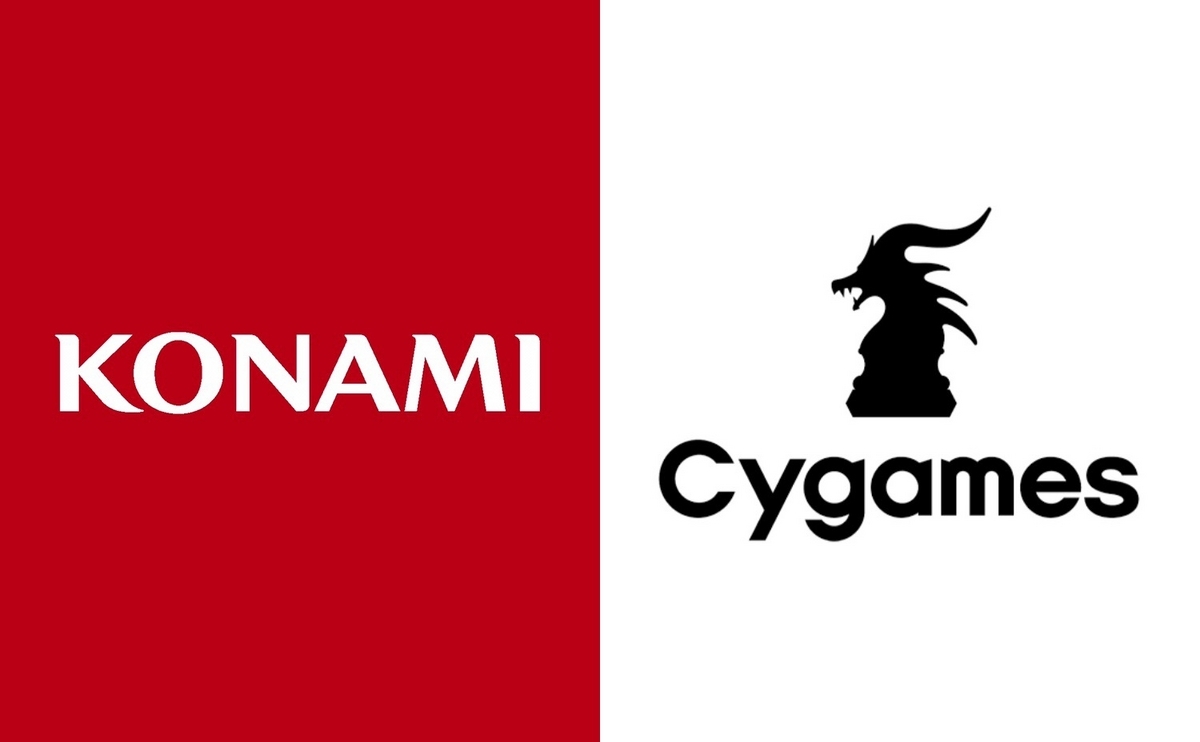2007年、ニンテンドーDSで発売されたミステリーアドベンチャーゲーム『ウィッシュルーム 天使の記憶』が再び注目を集めている。2025年初頭、海外版タイトル『Hotel Dusk: Room 215』が新たに商標出願されたことが判明し、往年のファンたちの間で「ついにシリーズに何らかの動きがあるのでは?」という期待の声が高まっている。
本稿では、作品の概要と魅力、商標出願の背景、そして今後の展開について、過去の経緯や独自の分析を交えつつ詳しく掘り下げていく。
物語を読むようにプレイする──『ウィッシュルーム』の魅力
『ウィッシュルーム 天使の記憶』は、リバーヒルソフト出身の開発者たちによって設立されたCING(シング)によって開発されたアドベンチャーゲームである。舞台は1979年、アメリカ・ロサンゼルス郊外にある古びたホテル「ホテル・ダスク」。プレイヤーは元ニューヨーク市警の刑事で、現在はセールスマンとして働くカイル・ハイドを操作し、一夜の間にホテルの宿泊客たちと交流しながら、彼らの抱える秘密と自身の過去に迫っていく。
本作の特徴の一つは、ニンテンドーDS本体を縦に持ち、まるで本を読むかのようなスタイルでゲームを進める点にある。タッチペンを使ってキャラクターと会話し、手帳にメモを取りながら謎を解いていくインターフェースは、当時としては非常に斬新だった。また、鉛筆スケッチのようなビジュアル表現は、静かな物語に深みと詩的な情感を与えており、これもまた本作の大きな魅力となっている。
シナリオは重厚かつ繊細で、キャラクター一人ひとりに緻密な背景が用意されている。表面的にはホテルの宿泊客たちとの交流が中心だが、それぞれのストーリーが巧妙にリンクしていき、最終的にはカイルの個人的な過去や宿命へと繋がっていく構成は、文学的とも言える完成度を誇る。
CINGというスタジオの功績と終焉
CINGは、『アナザーコード 2つの記憶』『アナザーコード:R 記憶の扉』など、良質なアドベンチャーゲームを複数手がけたスタジオである。キャラクター描写に優れたシナリオと、ユーザーの想像力を刺激する演出力は、多くのゲームファンに評価された。
しかし、商業的には必ずしも成功したとは言い難く、2010年にCINGは自己破産申請を行い、事実上の解散となった。『ウィッシュルーム』の続編である『ラストウィンドウ 真夜中の約束』は2010年に発売されたが、日本と欧州でのみの展開となり、北米市場には投入されなかった。これは販売元である任天堂の判断によるものであり、アドベンチャーゲームの市場性に対する慎重な姿勢がうかがえる。
商標出願の意味するものとは?
2025年に入り、「Hotel Dusk: Room 215」の商標が新たに出願されたことが判明した。この出願は米国特許商標庁(USPTO)のデータベースにて確認されたもので、申請者は任天堂。かつて本作のパブリッシャーであった任天堂がこのタイミングで商標を更新した理由には、いくつかの可能性が考えられる。
まず最も考えられるのは、リメイクあるいはリマスター作品の開発準備である。昨今、過去の名作ゲームを現行機種に移植する動きは活発化しており、特にニンテンドースイッチでのレトロゲーム展開はその最たる例である。『逆転裁判』シリーズのリマスターが成功を収めたことを踏まえれば、『ウィッシュルーム』もその流れに乗る可能性は十分にある。
また、Nintendo Switch Online向けに、DSやWiiタイトルのクラウドプレイ対応を見越した動きとも解釈できる。さらに夢のある推測としては、まったくの新作あるいはスピンオフ作品の制作に向けた布石である可能性も否定できない。
ファンの記憶に生き続ける“カイル・ハイド”
『ウィッシュルーム』シリーズの中心人物であるカイル・ハイドは、アドベンチャーゲーム史上でも稀に見る硬派でありながら人間味あふれるキャラクターだ。口数は少ないが正義感が強く、どこか影を背負った存在。その魅力は時を経ても色あせず、SNSや掲示板ではいまでも彼を主人公とした続編を望む声が後を絶たない。
実際、CINGのスタッフの中には現在もゲーム業界に携わっている人物も多く、もし任天堂がその中の誰かと再び協力する形でプロジェクトを立ち上げるのであれば、ファンにとっては非常に意義深い復活劇となるだろう。
結びに──記憶は、消えない
『ウィッシュルーム 天使の記憶』は、そのタイトルが象徴するように、「記憶」と「喪失」、「再生」というテーマを丹念に描いた作品である。商標出願という小さな動きが、作品の新たな展開への扉を開こうとしている今、その記憶は再び私たちの前に姿を現そうとしている。
ゲーム業界ではしばしば、「もう出ないだろう」と諦められていた作品が復活を遂げることがある。『ウィッシュルーム』もまた、そうした“奇跡”の対象となる日は近いのかもしれない。果たして再び、あのホテルの扉が開く日は来るのか──今はただ、静かにその兆しを見守ろう。