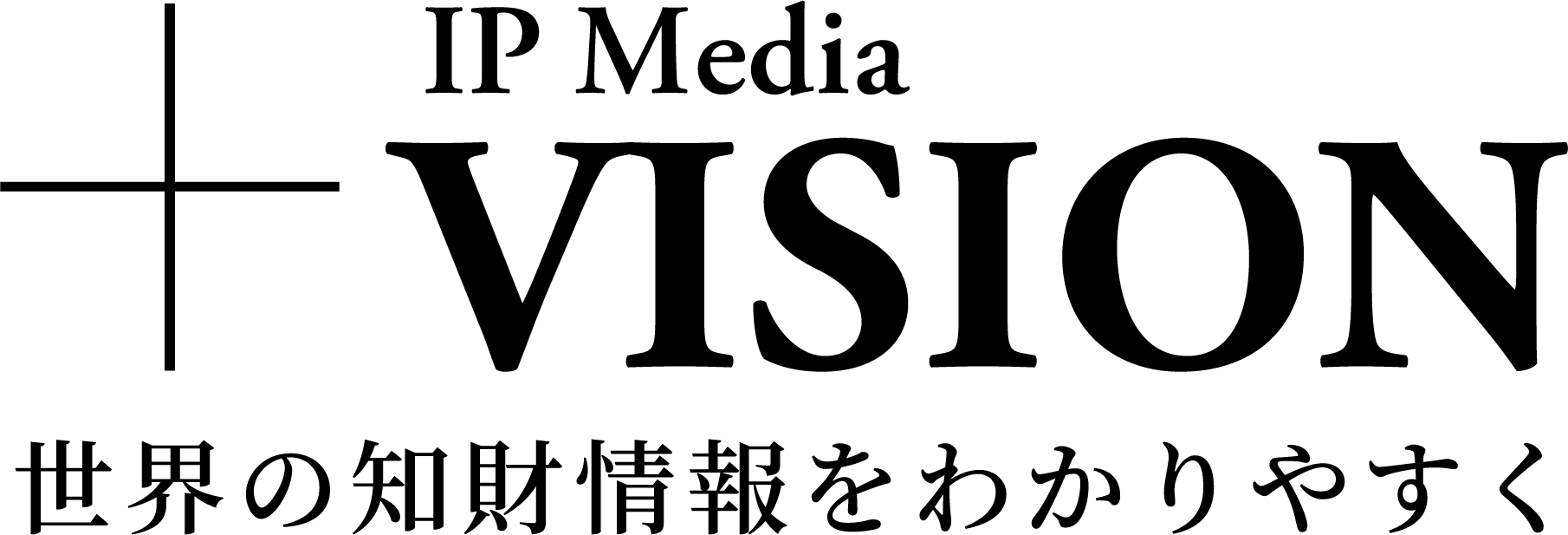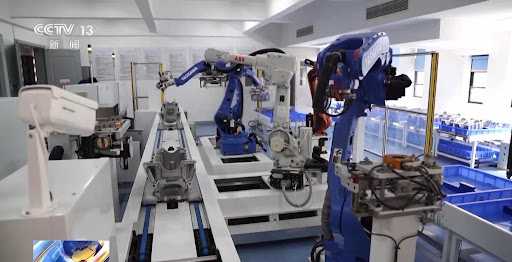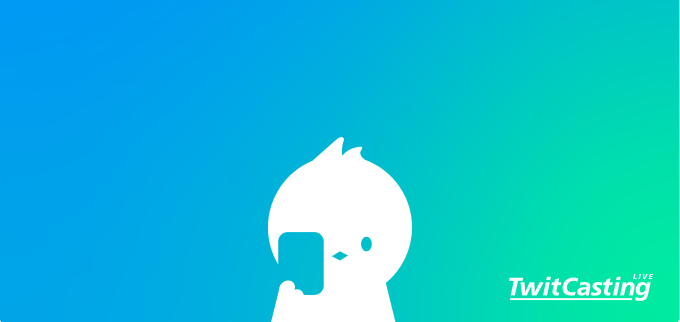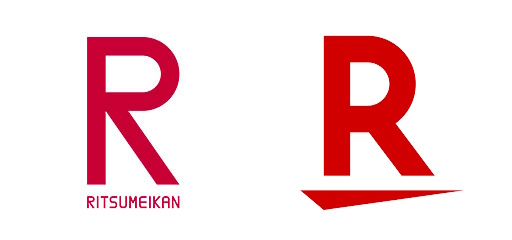2024年末、中国国家知的財産権局(CNIPA)は、人工知能(AI)が関与した発明について「特許出願が可能」とする見解を示し、知財界に大きな波紋を広げた。これまでもAIが発明に関与するケースは増加していたが、その法的な取り扱いは各国で分かれており、特に「発明者を人間に限るべきか否か」は、知財制度の根幹にかかわるテーマだった。
今回の中国の方針転換は、単なる出願受理の拡大を意味するだけではない。AIと知的財産の関係をめぐる国際的なルールメイキングに、中国が積極的な姿勢を見せ始めた兆しといえる。本稿では、AIが関与する発明の特許性をめぐる現状と課題、そして中国が描く“次の知財地図”について、独自の視点も交えて考察していく。
■ AI発明ブームと制度の“空白”
2020年代に入ってから、画像認識、創薬、素材開発、半導体設計など、AIが補助的または主体的に発明プロセスに関与するケースが急増している。その代表例が、南アフリカで特許を認められたAI「DABUS」による発明や、欧米各国で続いた同AIをめぐる法的論争だ。
多くの国では、現在も「発明者は自然人に限る」との立場をとっている。日本の特許庁も「AIは発明の手段として用いられるにとどまり、発明者にはなりえない」という方針を崩していない。一方、南アフリカやオーストラリアの一部裁判所では、AIによる発明を認める判断が下されたこともある(その後、上訴審で覆される例も)。
このように、AI発明をめぐる制度設計には国際的な統一がなく、企業にとっては「出す国によって特許の可否が分かれる」というリスクが存在していた。
■ 中国のCNIPAが示した柔軟な方針
こうした中、中国国家知的財産権局(CNIPA)は、AIが関与した発明について「発明者を人間とする形での出願であれば、AIの関与を理由に拒絶されることはない」とする見解を示した。これは形式的には「発明者はあくまで人間」という立場を維持しつつ、実質的にAI主導の発明の出願を可能にするものである。
さらに、審査実務上もAIを用いた発明に対しては「技術的思想に基づく創作」であれば特許性を否定しない、という方針が強調された。これにより、出願人が発明の過程においてAIが関与したことを開示したとしても、その事実自体で排除されるリスクは大きく減ったといえる。
この動きは、中国がAI技術の世界的な競争の中で、国内企業や研究機関の出願インセンティブを維持・強化しようとする戦略と一致している。
■ 「発明者」の再定義と、新たな責任論
中国の方針は一見すると「現行制度の枠内で柔軟に運用した」と捉えられがちだが、その含意は深い。AIが本質的に創作活動を担っていることを黙認する形で認めたという点では、今後の制度改革の布石とも読める。
とはいえ、AIが発明者として法的に認定されるか否かは、単なる技術問題ではなく、「誰に発明の帰属と責任を課すのか」という法哲学の問題でもある。たとえば、AIが予期せぬ技術的作用をもたらし、それが損害を引き起こした場合、「誰が責任を取るのか?」という問いに答えなければならない。
現状では、AIを開発・運用した人間(または企業)が責任主体として想定されるが、それが果たして妥当なのか、あるいは新たな制度的工夫が必要なのか、議論は続いている。
■ 独自視点:特許審査官にこそAIが必要な時代
AIによる発明が増える一方で、もう一つ重要な観点は「審査する側の体制」である。従来の人間中心の審査体制では、AIが生み出した複雑なアルゴリズムや発明内容を理解・評価することが難しくなりつつある。こうした背景から、欧州特許庁(EPO)や米国特許商標庁(USPTO)では、審査支援のためのAI導入が始まっている。
中国も例外ではない。むしろ、AIの審査支援に関しては世界でも先進的な取り組みを進めており、すでに画像認識や自動類似文献探索などをAIが担っているという。今後は、AIが生み出した発明をAIが審査する──そんな“自己完結的知財サイクル”が現実になる可能性もある。
この流れを踏まえれば、「AIが発明者となることは問題だ」とする旧来的な見解そのものが時代遅れとなる日は近いのかもしれない。
■ 国際競争と“AI特許大国”の行方
AI発明をめぐるルール形成は、知財の域を超え、国家間のテクノロジー覇権争いに直結している。中国が今回の方針を示した背景には、「AI関連特許の出願数で米国・欧州を圧倒したい」という戦略的な野心が透けて見える。
実際、WIPO(世界知的所有権機関)の統計でも、中国からのAI関連特許出願は世界でも群を抜いており、今後も制度的な優遇策が増えていけば、AI特許分野における“中華圏の黄金期”が訪れる可能性は高い。
これに対し、日本はどう動くのか。少なくとも「人間中心主義」の立場に固執したままでは、AI時代の知財主権を守ることは難しくなるだろう。
■ 終わりに:発明の未来と知財の変容
AIはすでに「発明者の補助役」から「共創パートナー」へ、さらに「独立した創作者」へと進化している。その現実に制度が追いついていないのが今の姿だ。
中国・CNIPAが示した柔軟な姿勢は、未来に向けた小さな一歩でありながら、技術と法の共進化における大きな意味を持つ。これを機に、他国も「AIとともにある発明とは何か」「誰が創造性を持ち得るのか」という根源的な問いと向き合わざるを得なくなるだろう。
「発明者とは誰か?」という問いは、もはや法律の世界だけの問題ではない。私たち一人ひとりが、AI時代の創造性について、再定義を迫られているのかもしれない。